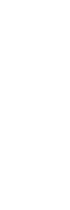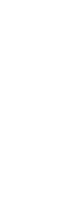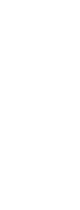時は、17世紀。
かの有名なイギリスの学者、アイザック・ニュートンが学位を取得したその時代、
人類を脅かすパンデミックが起こりました。
感染症、ペストです。
中世ヨーロッパにおいて多くの命を奪ったと言われるそれは、
「黒死病」として恐れられ、社会崩壊をもたらしました。
ロンドンでの1665年から1666年にかけての流行により、ニュートンが通う大学は閉鎖。
ニュートンは、故郷、ウールスソープへと避難します。
自由な思考で過ごすことができた時間は、ニュートンにごく当たり前の風景への疑問を抱かせます。
それは、庭にある木から落ちるりんご。
りんごは落ちたように見える。
しかし、実は落ちたのではなく、地球に引っ張られたのではないか。
そして、りんごも地球を引っ張っているのではないか。
「万有引力の法則」の着想です。
それをきっかけに、ニュートンは、3つの運動法則とされる力学、数学、光学を発見し、
「3大業績」として、歴史に刻まれました。
これらは全て、故郷で過ごした18ヶ月間のことであり、
その期間は「創造的休暇」と呼ばれています。
2020年、人類は、再び難局を迎えました。
日本のみならず、世界中で奪われた日常は、まるでその時と同じだったのではないかと思います。
今こそ、ニュートンのような思考が必要なのではないでしょうか。
当たり前だと思う風景、もの、こと、人などを、少し違った視点で見てみる、聴いてみる、
嗅いでみる、味わってみる、触ってみる、考えてみる、感じてみる。
ゆっくりと、じっくりと、時間を享受することによって生まれる自己との対峙。
河瀨直美、角田光代、石川直樹、皆川 明。
「紀寺の家」で過ごす、「創造的休暇」。
4人の物語が生まれます。
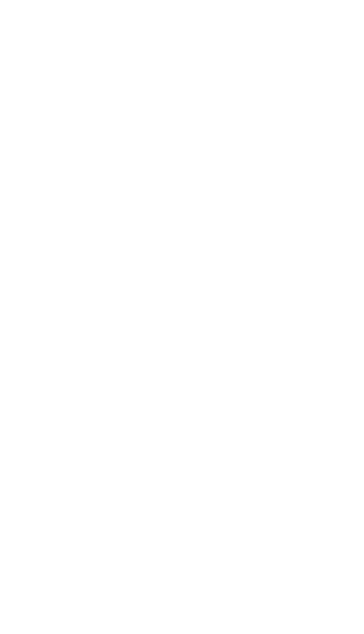
きおくと現実のはざまで
アテもない散歩、この辻を曲がれば何に出会えるのだろうと心弾ませていたあの日、私の笑顔はきっと穏やかで清々しい色をしていたに違いない。あの色にもう一度逢いにいく。でも、もう少し、だから、ここで頑張ってみる。そう思い、空を見上げるとまんまるなお月様がじっと私を見つめてくれていた。梢の向こうに輝くそれは、この地球に暮らす人々の上に等しく光を放つ。ああ、同じだね。大好きだよ。ここにいるよ。ありがとう。
映画監督 河瀨 直美
1969年生まれ、奈良県出身。地元・奈良を拠点に映画を創り続ける。一貫したリアリティの追求はカンヌ映画祭をはじめ、各国の映画祭で受賞多数。代表作は、「萌の朱雀」、「殯の森」、「2つ目の窓」、「あん」、「光」など。映画監督のほか、CM演出、エッセイ執筆などジャンルにこだわらず表現活動を続け、故郷奈良において「なら国際映画祭」をオーガナイズしながら次世代の育成にも力を入れている。最新作「朝が来る」は、第73回カンヌ映画祭公式セレクション、第93回米アカデミー賞国際長編映画賞候補、日本代表として選出。第44回日本アカデミー賞では、6部門で優秀賞と新人俳優賞を受賞。また、東京2020オリンピック公式映画監督に就任。2025年大阪・関西万博のプロデューサー兼シニアアドバイザー。バスケットボール女子日本リーグの会長も務める。プライベートでは、野菜やお米も作る一児の母。
www.kawasenaomi.com

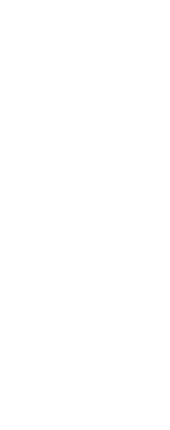
人とともに生きる町
奈良は広く、テーマごとに異なるスポットへの旅ができる。私は以前、万葉の旅や古事記の旅をしたことがある。範囲が広いので、車で要所要所を訪ねる旅だった。奈良の中心街を、テーマも目的も決めずに、じっくりと歩いてまわるのは、だから今回がはじめてだ。歩いてみて抱くのは、やっぱり、奇妙な町だという印象である。
宿泊した「紀寺の家」から一キロも歩かないうちに木々が頭上を覆う森が広がり、鹿が音もなく歩き、森の奥には春日大社があり、その向こうに原生林が広がる。春日大社から奈良公園を突っ切っていくと、大きな池があり、池を過ぎるとホテルや飲食店が増えてきて、あっという間ににぎやかな繁華街となる。繁華街のなかに小学校があり、神社がありお寺があり、長いアーケードがある。
何を奇妙に感じるのか、考える。あ、そうか、人に必要なすべてが、ぜんぶ等距離にあることだ、と気づく。人、というのは、今を生きる私たちが必要としたものばかりでなく、何百年、何千年もの昔を生きていた人たちがかつて必要としてきたものも、すべて、新古の別なく、聖俗の隔てなく、大小も広狭も関係なく、ひとしく配置されている。こうして書くと、ごくふつうのことのようだが、でもそんな町はめったにない。世界遺産や国宝や重要文化財が、町の至るところにあるけれど、その数の多さは、旅館や飲食店や雑貨店の多さと、意味合いとしておんなじだ。どちらも、この町に生きる人たちが必要とし、暮らしを支えてもらっている、拠りどころだ。
今と昔、それもはるか昔の暮らしが、違和感なく矛盾なく、ごくふつうに入り混じっている光景は、そのまま、未来の町をも浮かび上がらせる。奈良の町を歩きながら、私は未来を想像している。古きものと今のもののなかに、未来を生きる人たちが必要とするものも、ごくすんなりと入りこむのだろう。
そのことを、もっとも体感できるのは、紀寺の町のある一角、ならまちとよばれる地域ではないだろうか。道路に面した格子扉と瓦屋根が特徴の町家が、重要文化財、登録有形文化財も交えながらずらりと並び、ある家はごくふつうの民家、ある家は資料館、ある家は昔ながらの漢方薬局、ある家はカフェ、雑貨店、酒店と、まさに今と過去が「町家」のかたちを借りて入り交じっている。細い路地の先、行き止まりに見えつつ、さらに細い路地が左右に走っていたりする。路地から路地を歩いていると、野良猫になった気分だ。時空を自在にいききできる野良猫だ。
瓦屋根の上に広がる空がゆっくりとだいだい色に染まり、端から紺に変わっていく。私が見ている夕方は、百年前の、千年前の、もっと前の夕方ときっと同じだと確信する。
百年以上も前の建物で、湯が沸き冷暖房が完備された今の暮らしを体験できる「紀寺の家」は、まさに奈良という町をあらわすシンボル的存在だ。障子からさしこむやわらかな朝日とともに目覚め、おいしい朝ごはんをいただいて、格子をくぐって外に出て、過去と現在と未来を自在に歩く。すべての人にとって、そんな時間は創造的休暇になるだろう。
小説家 角田 光代
1967年生まれ、神奈川県出身。早稲田大学第一文学部卒業。1990年に「幸福な遊戯」にて海燕新人文学賞を受賞後、デビュー。以降、1996年「まどろむ夜のUFO」野間文芸新人賞、2003年「空中庭園」婦人公論文芸賞、2005年「対岸の彼女」直木賞、2006年「ロック母」川端康成文学賞、2007年「八日目の蟬」中央公論文芸賞、2011年「ツリーハウス」伊藤整文学賞、2012年「紙の月」柴田錬三郎賞、「かなたの子」泉鏡花文学賞、2014年「私のなかの彼女」河合隼雄物語賞を受賞。その他の著書には、「キッドナップ・ツアー」、「愛がなんだ」、「さがしもの」、「くまちゃん」、「空の拳」、「平凡」、「笹の舟で海をわたる」、「坂の途中の家」、「拳の先」など多数。近作は、新訳「源氏物語」(上中下)、連載小説「タラント」(読売新聞)。


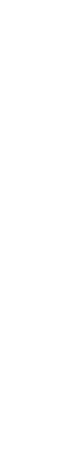
順応と回復の地
ヒマラヤのロッジでは、小さく堅い木のベッドの上に敷いた寝袋にくるまって眠る。でもここでは、畳の上に敷いたふかふかの布団で眠れる。寝返りを打っても床に落ちることはない。
ヒマラヤでは一週間同じ服を着続け、お湯で体を洗えるのも一週間に一回程度だった。それも、ちょろちょろと流れ落ちるだけの心もとないシャワーか、バケツに入れたお湯を体にかけるのみ。ここでは、タイル張りの五右衛門風呂にざぶんと浸かって、心ゆくまで体を温めることができた。
ヒマラヤの朝食は、かちこちの冷たいトーストに真っ赤なゼリーのようなジャムをつけて食べていた。ここでは、釜に入った出来立てのごはんをいただいた。味噌汁に入っている油揚げを口に入れただけで、幸せな気持ちになった。自分で淹れるコーヒーもお茶も、口にするあらゆるものが内臓に染みた。
朝、食事をしながら近くの学校のチャイムが聞こえた。縁側から庭を眺めていると、どこからともなく鳥の鳴き声が耳に入った。静かだけど、静かすぎないのがいい。誰かの生と隣り合わせに自分が在るということを思い出し、いま生きていることのありがたみを感じる。
二泊したうちの一日は、大雨で、風もことのほか強かった。その日、ぼくは縁側から、強風にかしぐ庭の木を、屋根から滴り落ちる水滴を、木の壁を叩く横殴りの雨粒をただ眺めてばかりいた。寒くない。つらくない。息苦しくない。毎日、数百メートルの高低差のある山道を何キロもひたすら歩き続けていた日々とは対極の時間を過ごしながら、しかし、頭の中ではこの先に広がる旅への思いが渦巻き、新しい考えが次から次へと浮かぶ。何もしていないのに、思考が縦横に巡り続けている状態、こうした時間に身を浸すことこそが自分にとっての「創造的な休暇」というのだろう。
厳しい遠征から帰った後は、生きていることを実感する特別な順応期間が必要で、紀寺の家はそれを十分にもたらしてくれた。またここに泊まりたい。そう思える空間がひとつ増えたことを、自分自身、喜んでいる。
写真家 石川 直樹
1977年生まれ、東京都出身。東京芸術大学大学院美術研究科博士後期課程修了。人類学、民俗学などの領域に関心を持ち、辺境から都市まであらゆる場所を旅しながら、作品を発表し続けている。2008年「NEW DIMENSION」(赤々舎)、「POLAR」(リトルモア)により日本写真協会賞新人賞、講談社出版文化賞、2011年「CORONA」(青土社)により土門拳賞を受賞。2020年「EVEREST」(CCCメディアハウス)、「まれびと」(小学館)により日本写真協会賞作家賞を受賞した。著書に、開高健ノンフィクション賞を受賞した「最後の冒険家」(集英社)ほか多数。2016年に水戸芸術館ではじまった大規模な個展「この星の光の地図を写す」が、新潟市美術館、市原湖畔美術館、高知県立美術館、北九州市立美術館、東京オペラシティ アートギャラリーを巡回。同名の写真集も刊行された。2020年には「たくさんのふしぎ/アラスカで一番高い山」(福音館書店)、「増補版 富士山にのぼる」(アリス館)を出版し、写真絵本の制作にも力を入れている。
www.straightree.com


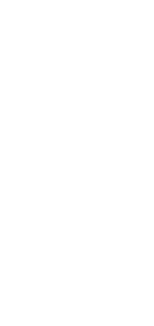
心が巡る時間
このコロナ禍以前は毎年6月頃一ヶ月程北欧へ出かけてまさに予定無しの時間を過ごしていた。その期間でも一週間ほどは現地でのリズムが気ぜわしくて落ち着かないのですがその後ようやく場に漂う気のままの心持ちになってそこからは小さな出会いや気づきからアイデアが気泡のようにふつふつと湧き始める感じだ。そうなると心は好奇心のままに行動と結びつき無意味な躊躇は消え、目の前の出会いや機会に自然と向き合おうとし始めようやくそこからが休息の時間になる。そして目に映るものに能動的な態度が自然な形で現れ、思いつけばその場で航空券を予約して知らない土地へも移動を開始する。全ての好奇心が不安を越えて行動が自転していく感覚になっていく。ひとりで行くのはそのペースを保つ為だ。その方が心と会話しやすく疲労や思考と向き合いやすくなる。そんな時間をこのコロナ禍で過ごせなくなる中で今回のお話を頂いた。前述したように心持ちが整うのに少し時間がかかるからこの二、三日の旅程の中でその状態を作れるだろうかと思いながらそれでも意識的に創造的休暇と思って過ごしてみることに関心があった。
初日は15時くらいに宿に到着して荷物を置いて先ずは散歩に出かけることにした。日常の仕事のリズムから離れる為にも。歩く速度も思考もゆっくりと。出会うという感覚は出会うべきものがそこにあるのではなく意識の隙間を通り抜けるカケラのようなものがたまたま脳裏に引っかかるようなものだと感じている。その引っかかったものをそっと摘んで眺めているとむくむくとそのカケラが頭の中の空想と繋がって今までの何かと結合しておぼろげな姿となるようなそんな感覚かもしれない。数ヶ月前に奈良に来た時に一度立ち寄ったカフェまでとりあえず歩いてその間に自分のこれからをぼんやり思いつくままに思い浮かべてみる。ただのんびりしてるだけでこれは創造的かと思いながらも今回何も起こらないのもまた私であると思いながら。目的がなくても動いていれば何かが起こり何かを思考し何かを想像する。カフェの店主のお母さまから手作りジャムを頂いた。小さな出来事も旅では澄んだ記憶になる。その足で駅の方へ向かい商店街を歩いていると白雪ふきんのオーナーの奥様とばったりお会いした。前回、奈良に来たのは白雪ふきんさんを訪ねる目的だったのでここでばったり会うのも変化の兆しだった。ひとりどこかで食事を済ませようと思っていたがオーナー夫妻が夕食にご招待いただき、その後遅くまで時間をご一緒いただいた。お互いの仕事や考えを共有できたことは日頃の打ち合わせでは得難い時間で有り難かった。それでもこれが創造的休暇なのかと言えばそうではないのだろう。でもこの予定外の時間が生まれる場の中に入ってきた感覚は何だか面白いと感じた。
そもそも創造的休暇とは何なのだろう。
それを目的とした時にその答えが見つかるのだろうか?抱いていた疑問がまた湧いてきた。でもその疑問はここへ来るまでとは少し違う穏やかでそして安気な気分の中にあった。翌日は朝食後に奈良公園へ散歩に出ることにした。1時間ほどベンチに腰掛けて本を読みこちらを見る鹿の親子と時折り目を合わせているうちに静かに流れている時間が身体に馴染んできたのがわかった。今日は只々歩いてみようと決めて心がこの静かなままに過ぎるように目に映るものをゆっくり見ては頭の中に反芻させてまた歩いた。通りすがる人も蝉の声も町の古い看板も微かに触れるように記憶されていくのがわかる。夕方に商店街のアーケードの2階にカフェがあるのに気づいて入った。そこにあった民俗学的な本を読み僅かなタイムトリップをしながらしばらく過ごした。このカフェに気づいたことで心がだいぶニュートラルになっているのがわかる。目的から解放された時に生まれる偶然を含んだ時間になっているのを感じたからだ。あと数時間で何か起こるだろうけどそれは創造的とはまた違うのだろう。それでも今のこの時間の延長線上にはもしかしたら創造的何かがあるのかもしれないとも思えた。帰り道もう閉店時間間際のアンティークショップを見つけて滑り込んでみる。最初に目についたのが僕がコペンハーゲンのアンティークショップで見つけたジョージ・ジェンセンの鳥のペーパーナイフだった。お店にはそれ以外が概ね日本の骨董だったからそれが目に飛び込んだのかもしれない。それにしてもそのペーパーナイフは僕の北欧の旅で出会った中でも大切なものだったからこの奈良での出会いに驚いた。今回自分が北欧での休暇とどこかで比較していることとがリンクしているような気がした。それでもあまりこじつけて意味を持たせたくなかったのでただ心地良さを素直に感じながら店を後にした。何故だか夕食を取る気にならずそのまま夕暮れの中をまたしばらく歩き紀寺の家に戻って風呂に入りぼんやりしながらこの二日間で企画していただいたような創造的な休暇には至らなかったけれど久しぶりに自分の心とずっと一緒に過ごせたような気がしてうれしかった。
旅や休暇で大きな気づきやアイデアが浮かぶとは限らないけれどその時間が心を解したり自由にしてあげる事はできる。そうしたら心が目的に縛られずに思いもしないことと出会うかもしれない。これからそんな時間を人生でもっと持ちたいと思うに至ったのが今回の僕の奈良での時間だった。今日は15キロ歩いたようだ。歩いた分をなぞりながら日頃ならば見落としているだろう細かな町の表情が浮かんできた。この微細な景色がこれからどうやって記憶としてトレースされ仕舞われていくのか楽しみだ。もしそのことが何か大きな気づきとなった時にはぜひお知らせしたい。
デザイナー 皆川 明
1967年生まれ、東京都出身。1995年に『minä perhonen(ミナ ペルホネン)』の前身である『minä』を設立。ハンドドローイングを主とする手作業の図案によるテキスタイルデザインを中心に、衣服をはじめ、家具や器、店舗や宿の空間ディレクションなど、日常に寄り添うデザイン活動を行っている。デンマークの『Kvadrat(クヴァドラ)』、スウェーデン『KLIPPAN(クリッパン)』などのテキスタイルブランド、イタリアの陶磁器ブランド『GINORI 1735 (ジノリ1735)』へのデザイン提供、新聞・雑誌の挿画なども手がける。
www.mina-perhonen.jp